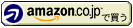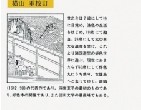三休橋筋
水の都・大阪は、大正時代には1600本を越える橋が存在した。古代大陸渡来の土木技術は日本の風土に合わせ受け継がれてきた。現在は姿を消したが、三休橋筋の名前の由来となる三休橋は長堀川に架かる橋だった。復元されたガス灯の照らす大阪・三休橋筋は、中之島公会堂から船場を貫き長堀通りまで道筋として残り、大正浪漫を今に伝えている。
大正浪漫は、19世紀のヨーロッパの美学とダダイズムの影響を受けた大正期の思想と文化の潮流。マーケットバリュー(市場価値)の創造を目指す、大正モダニズムとは対照的。

大阪市北区・中央区
TEL:06-6231-4881 (綿業会館)

東博百選
畿内七道
千夜千冊
Tags : 三休橋筋









 西鶴自身あるいは友人の西吟は、『好色一代男』を「転合書」と呼んでいた。転合とは「ふざける」「おかしい」「変な」「ざれごと」といった意味であるが、文字通り「転じて合わせる」ということでもあって、西鶴はこの世之介の物語を源氏五四帖に見立てる。
西鶴自身あるいは友人の西吟は、『好色一代男』を「転合書」と呼んでいた。転合とは「ふざける」「おかしい」「変な」「ざれごと」といった意味であるが、文字通り「転じて合わせる」ということでもあって、西鶴はこの世之介の物語を源氏五四帖に見立てる。