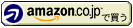-
聖護院の庭 浅井忠
明治37(1904)年 東京国立博物館蔵 高野時次氏寄贈 - 佐倉藩藩士の子供で花鳥画を学んだ浅井。文明開化で、パリ万博の監査官として留学したフランスから帰国後、... 続きを読む
- 『沖縄が誇る家宝の三線展』(2/5〜3/10)
- 「琉球三線楽器保存・育成会」の創立30周年を記念して、同会の主たる活動である三線鑑定会と文化財として... 続きを読む
-
染付雪景(ソメツケセッケイ)山水図皿(サンスイズサラ)
江戸時代 18世紀 東京国立博物館蔵 - モチーフは和様の鍋島焼には珍しい、中国の水墨画を手本とした絵画風で、鍋島焼の最盛期、18世紀初頭の作... 続きを読む




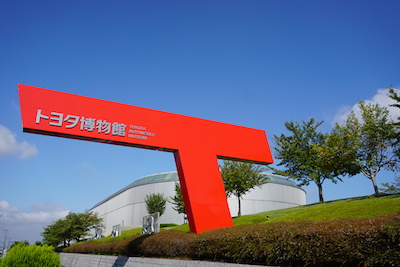




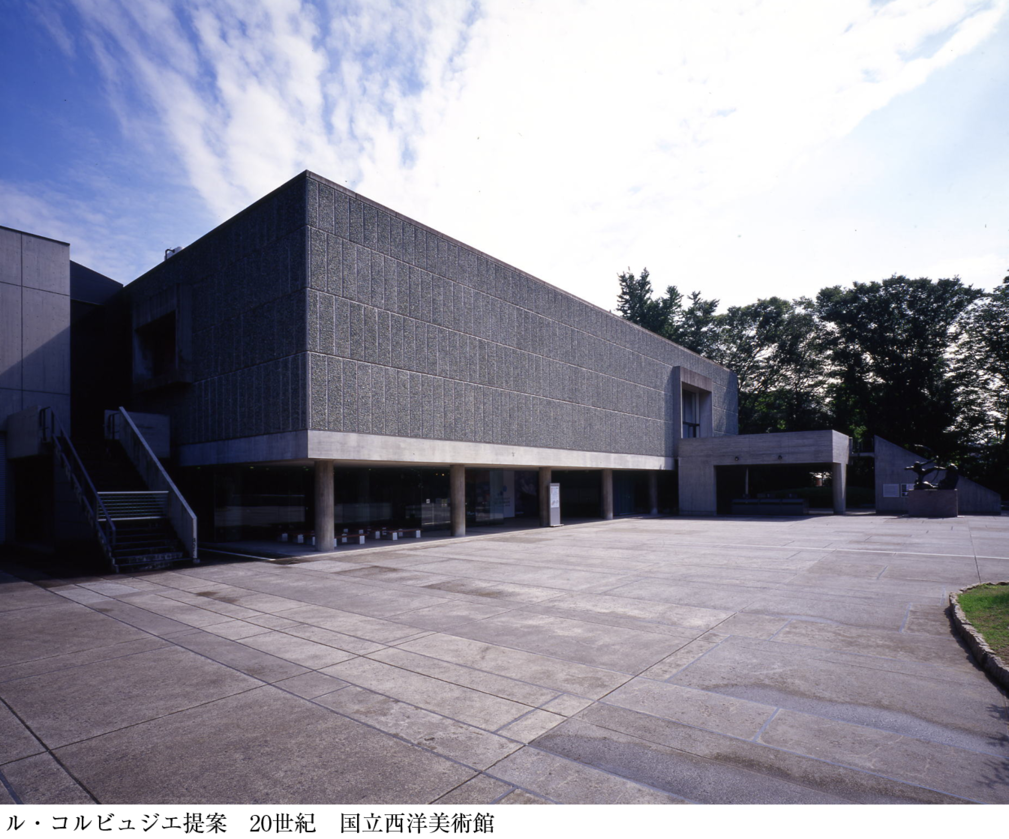
 1954(昭和29)年に実際に起きた滋賀の近江絹糸の労働争議をモデルにした小説。家族主義を標榜するワンマン社長に対し起こさされる労働争議。父親と息子、絹=日本的なものと明察=東洋的、西洋的な見識を対称し、「土着の心情」の価値や意味を提示する。そして絹のワンマン社長が、最後は明察に達するどんでん返し。
1954(昭和29)年に実際に起きた滋賀の近江絹糸の労働争議をモデルにした小説。家族主義を標榜するワンマン社長に対し起こさされる労働争議。父親と息子、絹=日本的なものと明察=東洋的、西洋的な見識を対称し、「土着の心情」の価値や意味を提示する。そして絹のワンマン社長が、最後は明察に達するどんでん返し。